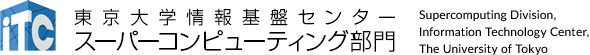2025年度若手・女性利用採択課題
このたびは、お申し込みをいただきどうもありがとうございました。以下の基準による厳正な審査のうえ、課題採択をさせていただきました(順不同)。
- スーパーコンピューターを利用することで学術的にインパクトがある成果を創出できると期待される点
- 大規模計算、テーマの重要性
2025年度(前期)
| 課題名 | 管の幾何に着目した変形物体の動力学の解明 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 寺田 雄(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-C・Wisteria/BDEC-01 Odyssey・Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| 微細加工技術の向上から、マイクロ流体デバイスの発展が目覚ましい。しかしながら、マイクロ流体デバイスの設計は試行錯誤によるものや、過去の成功例を踏襲したものがほとんどである。その原因は、曲がりや分岐などの複雑な流路構造をもつマイクロ流体デバイスにおける液滴や細胞、より一般に言えば変形物体の挙動に対する知見が不足しているためである。古くから直管における変形物体の挙動は理論や数値計算、実験において研究されており、種々の変形物体に働く流体力が研究されてきた。一方、曲がった流路中の変形物体を対象とした研究は数少なく、その動力学は未知である。本研究は、流路の曲がりに着目し、変形物体の動力学を明らかにすることを目的とする。第一に曲率が一定の流路において、パラメトリックに流路の曲率や変形物体の物性値の影響を評価し、変形物体の挙動を解明する。その後、任意の形状の流路において変形物体の挙動を数値的に解析し、流路の幾何と変形物体の軌跡の関係を解明する。 | |
| 課題名 | 分子動力学シミュレーションによるα-石英粒子間摩擦の研究 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 杉本 理空(東京大学 理学部) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| 物質の摩擦特性は速度・状態依存則(RSF則)で記述される。RSF則は経験則ゆえ、その適用範囲は実験が実施された温度・圧力・物質に限られ、特に地殻深部の高温高圧の震源領域への適用に限界があった。本課題の目標は、RSF Lawの理論背景解明に重要とされる、真実接触部での原子スケールの物理学から、震源領域に適用可能な摩擦則を構成することである。ここで地殻のような高温・高圧下で真実接触部での素過程を観察するのは難しい。そこで分子動力学計算から真実接触面での原子の挙動を調べ、物理的な素過程を抽出し、経験的であるRSF則に対して理論的なバックボーンを確立する。まず先行研究で、石英粒子が弾性変形すると仮定した場合は、真実接触面積は鉱物の弾性定数に依存すると考えられている。そこで、MDで地殻相当の高温高圧の石英の弾性定数を計算し、真実接触面積の温度・圧力依存性を調べる。ただ、高圧な地殻領域では弾性変形だけでなく塑性変形もすることも考えられる。そこで石英に人工的に原子の欠陥を入れることで塑性変形も再現し、さらに精度の良い摩擦則の構築を目指す。 | |
| 課題名 | 深層学習を利用した実験動物の行動解析法の開発 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 小林 幸司(東京大学 農学生命科学研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G |
| 実験動物の行動は精神・身体の状態を反映して変化するため、我々はそれを観察することで実験動物の状態を推定することができる。現在、脳や神経の機能を解明する基礎研究から、疾患の治療薬を開発する応用研究まで様々な分野において実験動物の行動観察が行われている。しかし、既存の行動観察試験は、研究者が自分の目で動物を観察して評価することによって行われており、多大な労力と時間がかかる上に客観性や再現性が乏しい。本研究では、実験動物の行動を録画した動画データをもとに深層学習を行い、自動的に行動を分類する方法を開発することを目的とする。 | |
| 課題名 | 反応性流体解析に向けた量子HPCハイブリッドアーキテクチャの創出 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 秋葉 貴輝(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G・Miyabi-C |
| 反応性流体は化学反応・プラズマ反応・核反応と流体現象が複合する複雑な系であり、その応用先は半導体プロセス・エネルギー利用・医工学など多岐にわたる。一方で、その非線形性や変数の膨大さから現代の大規模計算機を利用しても解析が困難である。そこで、近年目覚ましい発展が続く量子コンピュータに期待される膨大な計算性能をこうした反応性流体の解析に利用すべく、反応性流体向けの量子アルゴリズム技術の確立を目指す。反応性流体においては反応を記述する反応項が含まれ、一般に非線形性を有する。量子コンピュータは線型問題を取り扱うため、古典コンピュータによる線型化前処理が不可避であり、線型化された大規模問題を量子コンピュータで取り扱う量子・HPCハイブリッドアプリケーションが求められる。本課題では、その前段階として、古典コンピュータとGPUを用いた量子回路のエミュレーションを通じて本課題で提案する量子・HPCハイブリッドアルゴリズムの実用性を実証・評価する。 | |
| 課題名 | 大規模シミュレーションで探る新しい宇宙ひもの進化と宇宙誕生の謎 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 神田 行宏(東京大学 宇宙線研究所) |
| 利用システム | Miyabi-G |
| 宇宙ひもは、初期宇宙の相転移の痕跡であり、宇宙誕生の謎を探る鍵の1つである。本研究では、新しい種類の宇宙ひもである「埋め込みひも」の宇宙空間での振る舞いを、大規模シミュレーションによって解析する。埋め込みひもは、従来の研究で主に扱われてきた「位相欠陥の宇宙ひも」よりも豊かな構造をもち、近年の重力波観測の結果を説明可能な宇宙ひもとされているが、そのネットワークのダイナミクスは未解明である。本研究では、GPU並列計算を活用した3次元格子空間における大規模シミュレーションにより、埋め込みひもが形成するネットワークの進化を定量的に評価し、重力波観測を通した埋め込みひもの探索に向けた理論的基盤を確立する。 | |
| 課題名 | 機械学習型ポテンシャルを用いた分子動力学計算に基づく地球内部ダイナミクスの理解 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 矢澤 清太郎(東京大学 理学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G・Miyabi-C |
| 地球深部科学において天然物質や実験試料の多くが空孔や粒界を含む複雑な鉱物の集合体であり、地球深部と同等の高温高圧条件においてこのような鉱物の集合体の物性を理論的に求めることが求められている。密度汎関数理論に基づいた第一原理分子動力学計算は大きな計算量が必要となるが高温高圧条件で地球内部鉱物の物性を調べることができる手法である。しかし、粒界、空孔といった複雑な構造を含むような計算は大規模な系を必要とするため第一原理分子動力学計算では莫大な計算量が必要となりこのような系の物性解析には不向きであった。近年、機械学習を用いて第一原理計算結果を学習させることで分子動力学の計算時間を減らしつつ第一原理計算と同等の精度を担保する新たな計算手法が生まれ、大規模な系でも精度の良い計算が可能になりつつある。この手法を地球科学に応用し、これまでの計算量的障壁を超えてより実態に即した地球内部鉱物の物性を調べることが本課題の目的となる。 | |
| 課題名 | 気象モデルを用いたシビア現象の要因となる霰の生成に寄与する雲微物理プロセスの解明 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 近藤 誠(大阪大学 工学研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| 本研究では、降雹や雷の発生要因となる霰の生成・成長に寄与する雲微物理プロセスを、気象モデルを用いて解明することを目的とする。霰は積乱雲内で過冷却水滴を捕捉して生成され、成長することで雹となるほか、氷晶との衝突・反発による電荷分離は雷発生の要因となる。これらのシビア現象を理解するには、積乱雲内の雲微物理プロセスの詳細な解析が不可欠であるが、従来手法では多量の計算結果の解釈が困難であった。そこで本研究では、多変量解析手法であるRGBヘキサグラムを用い、雲微物理プロセスの寄与を可視化し、霰の生成に関与するプロセスを特定する。さらに、対象の雲システムや空間解像度を変更する感度実験を行い、シビア現象の発生につながる積乱雲の条件を明らかにする。 | |
| 課題名 | Sdiffフェーズを使用した波形インバージョンによる太平洋中央部下D″領域の地震波速度構造推定 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 大鶴 啓介(東京大学 理学系研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| 地球マントルの最下部数百kmの領域は核-マントル境界(CMB)直上の熱境界層をなしており、地球内部のダイナミクスや進化を理解する上で重要な領域である。これまでに行われた地震波による構造推定からは、アフリカ下と太平洋下の2箇所に巨大なS波低速度域(LLSVP)が存在することが知られているが、その成因については高温異常や初期地球物質などいくつかの仮説があるものの、はっきりとしたことはわかってない。LLSVPの成因を調べる上での困難の一つは、LLSVPが地震波データによるサンプリングの少ない領域に存在することにある。そこで本課題では、これまでマントル最下部の局所構造推定に使用されてきたS、ScSフェーズに加えて、新たにSdiffフェーズをデータとして使用する波形インバージョンの手法を開発し、これまで詳細な局所構造推定が行われていなかった太平洋中央部の下のマントル最下部領域のS波速度構造推定を行う。この手法の開発により、LLSVPのより広い領域が解像可能となり、LLSVPを含むマントル最下部のダイナミクスの理解が進展することが期待される。 | |
| 課題名 | NBIのRF負イオン源を対象としたPIC-MCCコードの構築 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 畠山 駿己(筑波大学 理工情報生命学術院) |
| 利用システム | Miyabi-G・Miyabi-C・Wisteria/BDEC-01 Odyssey・Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| 本研究課題では、無尽蔵のエネルギーとして期待される核融合の実現を目指す国際熱核融合実験炉(ITER)でも採用予定であるRF負イオン源のNBIを対象とし、PIC-MCC法による運動論シミュレーションで数値的に解析する。核融合炉の加熱で使用されるNBIでは負イオン源が用いられるが、その特徴として正イオン源に比べて高エネルギーでの中性化効率が高いことが知られている。しかし、プラズマグリッド付近のプラズマメニスカスに歪みがあれば、抽出される負イオンビームが発散されてしまう。このように、歪みが生じるようなメニスカスの発生機構は明らかになっていないことから、シミュレーションによって研究を行う。手法としては、磁気モデル推進機の計算モデルとしてシミュレーションの実績がある既存のPIC-MCCコードに対し、NBI用のモデルへの変更や電磁場の作成、ガス種の変更などを行うことで、RF負イオン源のPIC-MCCコードを構築する。今年度は昨年度に引き続き、PIC-MCCコードの構築を進めるとともに、計算モデルの形状を変化させながら、メニスカスやビーム散乱の影響に注目し、解析を行っていく。 | |
| 課題名 | ディープラーニングを用いた皮膚難病の診断・治療補助システムの開発に向けた基盤構築 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 中島 ひばり(東京大学 医学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G |
| 本研究課題では、皮膚難病の診断及び治療を補助するようなマルチモーダルAIの開発のための基盤構築を目指す。本学医学部附属病院皮膚科では、全身性強皮症や皮膚筋炎をはじめとする皮膚難病の診療を行っている。皮膚難病は皮膚に留まらず全身の臓器を侵し、患者さんのQOLや生命予後を大きく悪化させる。しかし、その診断は熟練した技術を必要とし、確立された治療方法はない。一方で、近年ディープラーニングを中心としたAIの発展は目覚ましく、限られた分野では医師を凌ぐような診断補助能力を示している。今回、GPU搭載の大規模計算機を用いてディープラーニングのモデルを使用し、皮膚難病に関する臨床情報や医用画像などマルチモーダルなデータを統合し解析することで、診断・治療をより正確にできるようなシステムを開発し、患者さんの健康上の利益を向上させることを目指す。将来的には、様々なモダリティの詳細なデータ解析を行うことで、皮膚難病の新たな機構解明及び創薬へと繋げていきたいという展望がある。 | |
| 課題名 | 地震波形インバージョンによるマントル最下部の異方性構造推定 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 佐藤 嶺(東京大学 理学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-C |
| 地球の核-マントル境界(CMB)は、固体岩石のマントルと液体鉄合金の外核が接する地球内部の最も主要な熱・化学組成境界であり、その直上数100km(D″領域)はマントル対流の下部熱境界層である。典型的な沈み込み領域下D″領域においては沈み込んだ海洋プレート(スラブ)が背景物質と相互作用することで熱・化学的な不均質を生成すると考えられているため、地球の熱・化学進化の理解に重要な領域である。D″領域でのスラブの流動方向を制約するには、三次元的な地震波の異方性速度構造をスラブの厚さと同程度の解像度で推定する必要がある。しかし、既存の異方性構造推定手法では計算コストの関係から三次元構造推定それ自体が困難もしくは、全球スケールの粗い解像度での構造推定にとどまっていた。本申請研究では地震波形に含まれる情報を余すことなく活用できる波形インバージョン手法と、スペクトル要素法による理論地震波形計算ソフトウェアSPECFEM3D_GLOBEを用いてD″領域の異方性速度構造をスラブの厚さと同程度の高解像度で推定する。 | |
| 課題名 | 波形インバージョン法を用いた内核境界近傍の3次元構造推定 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 大林 徹(東京大学 理学系研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| 本研究の目的は波形インバージョン法を用いて複数の地域下の内核境界(ICB)近傍の3次元不均質構造を固体・液体領域で同時推定し、地球核の熱化学進化の理解に貢献することである。そのために本研究ではまず、現在固体領域の構造推定に用いられている波形インバージョン法を液体領域にも適用できるように拡張する。その後、固体領域と液体領域の構造推定手法を組み合わせて固体液体同時構造推定手法を開発する。それを用いて、ICB近傍の局所的な3次元地震波速度構造推定を複数の地域で行う。内核の成長様式を理解するためにICB近傍で鉛直方向50kmの解像度が必要なので、計画段階ではICBの上下500kmを鉛直方向50km、水平方向100kmのグリッドに区切り構造推定を行う予定である。得られた速度構造をICB近傍の鉄合金についての鉱物物理学の知見と比較することでICB近傍の熱的・化学的構造を推定する。また、国内でICB近傍の研究をしている研究者は限られるため国内外の研究者と議論することでこの推定結果から内核の結晶化様式を理解し地球の成長史に制約を与える。 | |
| 課題名 | 超高解像度磁気回転乱流シミュレーションによる粘性係数の数値収束の調査 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 川面 洋平(宇都宮大学) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Odyssey・Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| ブラックホール等の周辺に形成される降着円盤では、ガスが中心天体へと落下する過程で重力ポテンシャルエネルギーが熱エネルギーに変換され、電磁波を放射する。この現象を理解する上で重要なのが、角運動量保存を破る磁気回転不安定性(MRI)による乱流が生み出す粘性係数である。しかし、粘性係数の値を正確に決定することができなかった。応募者らは世界最高解像度のMRI乱流シミュレーションを実施し、初めて慣性領域の解像に成功した。本研究では、応募者が開発した高精度かつ高並列性能を持つ擬スペクトル法コードCALLIOPEを用いて、長時間シミュレーションを行い、MRI乱流における粘性係数の収束値を決定することを目指す。既存の研究では慣性領域の解像に成功した例がなく、本研究は独創性が高い。また、粘性係数の決定には長時間の時間発展計算が必要となるため、挑戦的な研究であると言える。この研究により、降着円盤における放射強度の予測精度向上が期待される。 | |
| 課題名 | Mambaを用いた画像認識における画像特性の影響評価 |
|---|---|
| 氏名(所属) | アドルノ レオナルド(神奈川工科大学 情報学部) |
| 利用システム | Miyabi-G |
| 深層学習を用いた画像認識では、当初はCNNが主に利用されていたが、Transformerが提案されて以降、特に大規模モデルではTransformerの利用が主である。しかし、Transformerは系列長の2次のオーダーのメモリ量が必要となる課題がある。近年提案された状態空間モデルを基にしたMambは、系列長の1次のオーダーのメモリ量で済むという利点があり、急速にその活用が広まっている。しかし、Mambaへの入力は1次元に限られているため、2次元情報である画像をどのように扱うかが課題の一つである。画像を複数方向からスキャンして入力・統合する処理などが提案されているが、まだ最適な扱いについては定まっていない。本課題では、走査方法の工夫だけでなく、画像そのものに対して加工することで、Mambaの特性に合わせた画像の入力の在り方について検討する。具体的には、画像に人の視覚特性などを反映した前処理を施した上で入力することで、Mambaを用いた画像認識の性能や特性について評価する。 | |
| 課題名 | RANSとLESを用いたディンプル付きチャネルにおける脈動条件とディンプル面形状の多目的最適化 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 井上 昂典(東京農工大学) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| 現在、再生可能エネルギーが普及しているが、これは天候などにより発電量が大きく変動し不安定である。これに対してガスタービンはこのような負荷変動に対応できる調整用電源であるため、重要性が増している。ガスタービンの高性能化に伴い、燃焼ガス温度が上昇しており、タービン翼はその熱負荷にさらされるため、冷却技術の向上は必須である。先行研究で、チャネル片壁面へのティアドロップディンプル敷設と流れの脈動化により伝熱総合性能の向上が確認された。そこで、本研究ではタービン翼の冷却手法の一つである内部冷却において、冷却性能の向上と圧力損失の低減を満たす脈動条件やディンプル面形状の最適解を数値計算を用いて明らかにする。先行研究では、ディンプル面形状においてディンプルシフト量とディンプル面回転角度の2つの設計変数を設けて最適化計算を行っている。本研究では、これにディンプル深さのパラメータも加えた3つの設計変数で最適化計算を行う。また、得られたパレート解のいくつかの幾何学形状において、LESによる解析結果の検証と流れ場の考察を行う。 | |
| 課題名 | Enhancing Scientific Understanding in LLMs Through Structured Knowledge Graphs |
|---|---|
| 氏名(所属) | GAO FAN(東京大学 情報理工学系研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| Large Language Models (LLMs) sometimes struggle with factual accuracy, limiting their reliability in scientific and educational applications. This research integrates knowledge graphs (KGs) to enhance LLMs through structured knowledge retrieval and retrieval-augmented generation (RAG). By reducing hallucinations, our approach improves scientific QA, fact verification, and AI-driven tutoring, ensuring more accurate and trustworthy AI-generated content. | |
| 課題名 | 新規粗視化分子動力学法による微小管核形成過程の包括的理解 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 手代木 陽介(東京大学 農学生命科学研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G・Miyabi-C |
| 微小管は、多くの細胞活動の維持において必須となる構造体である。α/βチューブリン二量体は微小管の構成単位であり、GTPまたはGDPが結合する。微小管の構造体形成過程は、核形成・伸長という二段階の過程からなる。核形成は、α/βチューブリン二量体が重合し微小管前駆体を形成する過程であり、一方で伸長は微小管前駆体から構造体サイズを巨大化させる過程である。さらに核形成においては、自発的核形成とテンプレート型核形成の2種類の過程が知られている。核形成は、伸長過程と比較して実験的にも計算的にも扱いが困難であり、未だ研究例が少ない。そこで本利用課題では、申請者が独自に開発した新規粗視化分子動力学法を利用し、自発的核形成とテンプレート型核形成の2種類の核形成過程の統一的な理解を目指す。開発した手法は、従来のMDシミュレーションでは困難であるような、長時間かつ多分子存在下でのシミュレーションを可能にし、核形成過程への適用に適している。本研究課題の達成により、微小管の核形成過程における詳細な分子メカニズムが明らかになると期待され、今後分子混雑環境での再現や疾患との関連性といった研究に発展しうる。 | |
| 課題名 | 二次元遷移金属ダイカルコゲナイドの元素ドーピングの第一原理設計 |
|---|---|
| 氏名(所属) | Soungmin Bae(東北大学 金属材料研究所) |
| 利用システム | Miyabi-C・Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| 現在、半導体デバイスの微細化がシリコン技術の限界に近づく中、従来を超える新材料設計が求められている。特に、二次元遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)は極薄構造ながら高導電性を示し、次世代トランジスタのチャネル材料として有望である。しかし、高いコンタクト抵抗やキャリア移動度の制限といった課題を抱えており、不純物ドーピングによる物性最適化が必要である。本研究では、大規模な第一原理計算を用いて広範囲な点欠陥計算により不純物ドーピングの計算によるTMD物質全般のドーピング設計を行う。ハイスループット計算による27種類の安定構造を網羅的に探索することで、どのようなドーピングプロセスがTMDのn型・p型化を実現する条件を明らかにする。本研究により、二次元半導体の物性制御の理論的基盤を構築し、実験プロセスの最適化と次世代デバイス実現に寄与する。 | |
| 課題名 | 時空間スケール分離に基づく高レイノルズ数翼型失速流れ解析 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 玉置 義治(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| 本申請課題では、高レイノルズ数翼型失速流れ解析に対する時空間スケール分離に基づく効率的な解析フレームワークを実証する。高レイノルズ数の翼型周り流れでは、翼型前縁で生じる小スケールの乱流遷移現象と翼型全体スケールの空力現象が同時に存在している。ここで、乱流遷移現象については直接数値シミュレーション(DNS)、翼型全体の流れ場に対しては壁面モデルLESを用い、壁面モデルLESに対してDNSから得られる境界層を流入条件として与えることで、全体をDNSで解くのと比べて計算全体としてのコストを削減する(空間スケール分離)。さらに、遷移は時間スケールの短い現象であるため、DNSを全時間に渡って解く必要はない。ここでは、壁面モデルLESに対して、DNSから得られる流入境界層の平均速度や変動を合成乱流として与えることで、DNSを短時間に留め(時間スケール分離)、さらに効率的な解析を実現する。 | |
| 課題名 | FontGrid: a novel representation for large-scale in-the-wild font generation |
|---|---|
| 氏名(所属) | SHEN I-Chao(東京大学 情報理工学系研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| Existing font generative models use raster or vector font representations, but suffer from lack of salient features, such as sharp corner and straight lines or requires specialized architecture to deal with irrgular topologies. In this project, we propose FontGrid, a novel representation that has the advantages of both traditional representations. Specifically, FontGrid representation can be used with commonly used simple generative models using only small-scale dataset. | |
| 課題名 | 特定のeHMI向けカスタマイズLLMの訓練 |
|---|---|
| 氏名(所属) | Gui Xinyue(東京大学 情報理工学系研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| 本研究は、無人自動車と歩行者間のインタラクション効率を向上させるために、完全に自動化されたLLM(大規模言語モデル)駆動型のeHMIシステムの開発を目指しています。eHMI(外部ヒューマン・マシン・インターフェース)は、自動車と周囲の人々のコミュニケーションを円滑にするためのシステムで、これにより歩行者や周囲の人々に車両の意図や状況を伝えることができます。本研究では、特定のeHMIタイプに特化した小型で専門的なLLMのトレーニングを提案しており、これによりコスト効率の良い、実際の自動車に導入しやすいシステムの実現を目指します。このアプローチは、研究者や業界のために貴重な指針を提供することができます。また、センターの高性能コンピューティングリソースを活用することで、専用のLLMを迅速にトレーニングおよび微調整し、実験時間を大幅に短縮できます。このリソースを利用することで、さまざまなモデルアーキテクチャやハイパーパラメータを探索することが可能になり、より効果的なシステム開発が進むと考えています。 | |
| 課題名 | アルカリ水電解電極表面における酸素気泡の脱離モデルの構築 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 鈴木 雄介(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| アルカリ水電解は、グリーン水素製造の有望な手法であるが、高電流密度運転時に電極表面の酸素気泡によりエネルギー変換効率が低下する課題がある。先行研究や本研究チームの実験から、気泡の脱離は主に気泡同士の合体によって生じることが確認されている。合体時の表面エネルギー変化と粘性散逸のバランスによる気泡跳躍の予測理論は実験結果と整合するものの、電極への気泡の再付着現象は説明できていない。本研究の目的は、表面エネルギー変化と粘性散逸のより詳細な評価、及びそれら以外の気泡挙動への影響因子を実験的に解明し、気泡脱離を定量的に予測する物理モデルを構築することである。微細パターン電極と高速度カメラを用いた気泡挙動の観察により、静電気力やMarangoni力の寄与を評価し、これらを含む物理モデルを構築する。また、OpenFOAMを用いた数値解析により、気泡合体時の周囲流体の速度・圧力場を求め、表面エネルギー変化と粘性散逸、気体にはたらく流体力を評価する。さらに、電解液濃度場、電場の影響を考慮したモデルをソルバに実装して数値計算を行う。数値計算と実験結果を比較し、構築した物理モデルの妥当性を検証する。 | |
| 課題名 | ダイポール磁場中の電子ー陽電子プラズマの数値解析に向けたpartilcle-in-cell計算コードの構築 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 江本 一磨(核融合科学研究所) |
| 利用システム | Miyabi-G・Miyabi-C・Wisteria/BDEC-01 Odyssey・Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| 室内実験でダイポール磁場中の電子ー陽電子プラズマを実現する試みが行われている。等質量のペアプラズマに関する基礎研究であり、宇宙プラズマとも関連する。この電子ー陽電子プラズマは密度が10の11乗程度であり、運動論的な物理が予想される。本研究では、運動論的なプラズマを解析する手法として知られるparticle-in-cell (PIC) 法を採用し、ダイポール磁場中の電子ー陽電子プラズマを数値的に解析する。荷電粒子が作る自発電場とダイポール磁場によるLorentz力を考慮し、運動方程式とMaxwell方程式から自己矛盾なくプラズマダイナミクスを再現する。得られる計算結果としては、ダイポール磁場中の密度・温度・ポテンシャルなどの空間分布が想定される。また、局所的なポテンシャル揺動が明らかになることも期待される。 | |
| 課題名 | Kibble-Zurek機構に基づいた、トポロジカルマグノンの中性子散乱による検出法の提案 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 江崎 蘭世(東京大学 理学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-C |
| 近年、磁性体中の素励起であるマグノンのバンド構造のトポロジーに関する研究が盛んに行われているが、それを反映した特徴的な表面状態の観測の方法はいまだに確立されていない。そこで、申請者は中性子散乱を用いたマグノンのトポロジー由来の表面状態の検出法を理論的に提案する。中性子散乱は、磁性体のprobeとして非常に一般的な手法ではあるものの、基本的にはBulkの物理量を見ることしかできず、表面状態を検出することは難しいとされてきた。そこで、本研究提案では、容易軸異方性をもつ強磁性体の相転移温度付近で系を急冷することで、up spinとdown spinの多数のdomainが生じることに着目する。その場合にはdomainの境界にBulkのトポロジーに由来した境界束縛モードが現れることが予想される。このようなBulk中に生じるトポロジー由来の境界束縛モードのスペクトルは、制御された急冷のもとでKibble-Zurek機構に従って巨視的に多数のdomainが存在する場合には増強され、中性子散乱によって検出可能であることが期待される。 | |
| 課題名 | Prevention and Mitigation |
|---|---|
| 氏名(所属) | Geng Haopeng(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G |
| We propose a novel framework for evaluating L2 speech intelligibility by simulating native speaker shadowing using sequence-to-sequence voice conversion. Traditional ASR-based approaches often miss subtle perceptual cues, limiting their effectiveness for language learning. Our method integrates self-supervised speech representations and multi-task learning to jointly capture acoustic and linguistic features, thus identifying regions of perceptual ambiguity in nonnative speech. We further explore | |
| 課題名 | グラフ基盤モデルの構築と応用研究 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 金刺 宏樹(東京大学 情報基盤センター) |
| 利用システム | mdx |
| 本研究では、グラフデータ向けの汎用基盤モデル(GFM)を構築し、言語や画像分野で用いられてきた基盤モデルをグラフ領域にも適用する手法を探求する。具体的には、ノードやエッジに含まれるテキスト・時系列情報を大規模言語モデル(LLM)で統一的にエンコードし、グラフニューラルネットワーク(GNN)とjoint learning するアーキテクチャを提案することで、異なるグラフのセマンティクスを一貫して扱える表現学習を実現する。また、既存のTransformer 系モデルにグラフ構造情報を組み込む手法も検討し、汎用的な基盤モデルの拡張性を高める。これらの手法を、推薦システムや医療データなど実際に大規模なグラフを含む下流タスクに適用し、モデル性能とスケーラビリティを最適化することで、グラフ構造を活用するあらゆる応用分野への普遍的な基盤モデルの実現を目指す。 | |
| 課題名 | Large Language Model-driven Interpretable Multi-Modal Decision Support System for Disaster |
|---|---|
| 氏名(所属) | ZHAO XINJIE(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | mdx |
| Large-scale disasters, from floods to earthquakes, demand data-driven responses.. Our project harnesses an innovative synergy of Large Language Models (LLMs) and multi-modal data̶satellite imagery, real-time sensor feeds, and textual alerts̶to deliver transparent, context-specific decision support. By merging advanced AI algorithms with domain expertise, we enable swift risk assessment, resource allocation, and dynamic adaptation, thus transforming global disaster prevention and mitigation. | |
2025年度(インターン)
| 課題名 | 探索アルゴリズムの性能検証 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 下田 卓弥(東京大学 総合文化研究科) |
| 利用システム | Miyabi-C・Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| 探索とは、ある初期状態から目的状態へと至る経路や解を見つけ出す手法であり、人工知能やプランニング、ロボットなど幅広い分野で応用されている。充足解を求める代表的手法として、Greedy Best-First Search(GBFS)が知られている。これを並列化した代表的手法であるK-Parallel GBFS(KPGBFS)は、多くの場合、逐次版のGBFSよりも高速に問題を解けるが、逐次GBFSとは異なる振る舞いをすることで、桁違いに多くのノードを展開してしまう場合がある。(探索効率はスレッド数を増やすほど悪くなる。)私はこの問題を解決するため、展開ノード数を逐次GBFSの最悪ケース(+α)に抑える保証を持つ並列探索アルゴリズムOne Bench At a Time with SGE (OBATs)を開発した。OBATsは理論的な保証を備えつつも、平均的な探索性能はKPGBFSと同程度であり、実用性も高い。これらの手法についてコア数が多い場合どうなるか検証するため、スーパーコンピューターを用いて大規模実験を行いたい。 | |
| 課題名 | 自己回帰的な画像生成の探索 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 苗 中濤(東京大学 情報理工学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G |
| 近年、自然言語処理における大規模言語モデル(LLM)の発展により、コーディング支援や文書生成など、様々なアプリケーションで優れた性能が実証されている。これらは「次トークン予測」という自己回帰的な生成パラダイムに基づいており、その統一的な枠組みは多くの応用を可能にしてきた。一方で、視覚モダリティにおいては、このパラダイムに基づく統一的なマルチモーダル理解・生成の枠組みは未だ十分に確立されておらず、特に自己回帰的な画像生成の研究は発展途上である。本研究では、高次の情報と階層的な情報を統合するImage Tokenizerと、このトークナイザに基づく自己回帰型の画像生成手法を提案する。 | |
| 課題名 | Large Scale Simulation of Bubbly Flows in Slightly Inclined Vertical Channel |
|---|---|
| 氏名(所属) | ZHANG Hanyue(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| In deep-sea mining, air-lift pumps rely on bubbly flows in long pipes, which may incline because of underwater currents. However, their behavior in slightly inclined long pipes remains poorly understood due to experiment limitation. This study uses direct numerical simulation to analyze flow structure, bubble dynamics and forces in vertically oriented channels with extremely small inclinations (0–5°), aiming to improve gas-lift drift mathematic model and guide the design of air-lift pum p system | |
| 課題名 | 準動的地震サイクルシミュレーションを用いた分岐断層が主断層に与える影響 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 高橋 宗茂(東京大学 理学系研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| トルコの東アナトリア断層帯(EAFZ)では主断層から分岐・並行する断層が存在し、EAFZの南西部ではNarlı・Yesemek断層と呼ばれる分岐断層が主断層に対し約150kmにわたり並行している。2023年に発生したMw7.8の地震は逆問題の結果からNarlı断層から破壊が発生、その後主断層の両側へ破壊が伝播した観測事実が知られている。EAFZの南西部では1822年に地震が発生したが、破壊された断層に関しては今なお議論が生じている。当地域の準動的地震サイクルシミュレーションを用いた先行研究は存在するものの、主断層のみをモデリングの対象としており、結果として2023年の地震における上記の特徴を再現しておらず、また1822年の歴史地震に対し地質学的・古地震学的な観測記録とモデル内の断層挙動が整合しない。そこで本研究ではEAFZにおける準動的地震サイクルシミュレーションを、主断層に加えNarlı・Yesemek断層を含めた断層モデルを用いて実施し、1822年・2023年のイベントのすべり挙動が説明できるかどうか検証を行うと共に、摩擦特性・断層形状等が破壊伝播与える影響に関しても検証を行う。 | |
| 課題名 | 血管分岐部における血小板のマージネーション現象の機序解明 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 石川 浩史(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| 微小血管内では、血小板が血管壁近傍に多く分布する血小板のマージネーション現象が一般に観測される。壁近傍での血小板濃度の上昇は血小板の血管壁付着を直接的に増加させ、血栓形成において重要な役割を果たす。脳梗塞に代表される血栓症の予防に向けて、血小板のマージネーションのメカニズムの解明が盛んに取り組まれてきた。しかし、従来研究の大半は直管における解析を対象としており、血管分岐部において血栓が形成されやすいとの報告がある一方で、血管分岐部を含めた血栓に関する理解は依然として乏しい。本課題では、血管分岐部における血小板のマージネーション現象の機序の解明を目的としている。流体力学的な視点から、血管の分岐による断面内二次流れ、血球の変形流動、血球同士間の流体力学相互作用に着目し、現象の解明を目指す。 | |
| 課題名 | 大規模分散GPU環境を念頭に置いた機械学習型全球数値予報モデルの開発及び関連ライブラリの開発 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 上条 藍悠(東京大学 大気海洋研究所) |
| 利用システム | Miyabi-G・Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| 機械学習型全球数値予報モデルにおいては,その高解像度化を阻むのは分散学習時の通信量の増大である。今後数百数千というGPUを使用し,現在の最先端数値予報モデルで扱われているようなkm解像度のデータを扱える機械学習型全球数値予報モデルを作成するうえで,通信をほとんど必要としない局地的なモデルアーキテクチャと,より荒い解像度のHEALPix格子データ上での分散型球面調和関数変換+波数空間内ネットワークの機械学習アーキテクチャを融合させたモデルを作成することこそが必要不可欠であると考えた。 また,それに用いるHEALPix格子対応のGPU分散型球面調和関数変換ライブラリは私が調査した限り存在しない。よってそのライブラリも含めて機械学習型全球数値予報モデルを作成する。 | |
2025年度(後期)
| 課題名 | 周辺大気の環境条件と対流雲内部の雲微物理過程とを繋ぐ物理機構の数値的解明 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 鵜沼 昂(気象庁 気象研究所) |
| 利用システム | Miyabi-C |
| 大気中の雲・降水過程の結果として生じる降水現象は、時に激しい降雨を引き起こす。雲・降水過程を表現する上で重要かつ基礎的な物理量の一つに、降水粒子の粒径毎の頻度を示した分布(粒径分布)がある。気象レーダーや地上観測から間接的或いは直接的な粒径分布の把握が試みられてきているものの、その時空間的な変動の観測・推定には測器自体の制約を大きく受ける。加えて、雲・降水過程は周辺大気の環境条件にも影響を受ける。このため、周辺大気の環境条件と対流雲内部の粒径分布とがどのように相互作用しているかについては、観測事実のみでは十分な把握が困難であった。そこで、多様な粒形分布を許容可能な雲微物理スキームを用いることにより、観測事実を基に理想化した条件下で、大気モデルの数値シミュレーションを実施する。気温や湿度、風向・風速といった初期に与える大気条件の応答結果としての対流雲の強度や構造、及び対流雲に内在する雲微物理特性を把握する。そして、大雨をもたらした対流雲について、その内部で降雨が強化される場合の物理機構を粒径分布の観点から明らかにする。 | |
| 課題名 | GSPOを用いた教師なし機械翻訳におけるオフターゲット問題の克服 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 大瀧 望央(東京大学 情報理工学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G |
| 大規模言語モデル(LLM)を用いた機械翻訳は高い性能を達成しているが、その性能は大規模なパラレルコーパスに依存している。この依存性を克服するため、本研究は、正解訳文を必要としないモノリンガルコーパスのみで翻訳性能を向上させる手法を提案する。具体的には、強化学習のアルゴリズムであるGSPO (Group Sequence Policy Optimization)を翻訳モデルに適用する。この手法は、翻訳文の流暢さや意味的な正確さを評価する外部の報酬モデルを用いることで、パラレルコーパスに頼らず学習を進めることが可能となる。しかしながら、このアプローチには、報酬モデルが意図しない言語を高評価してしまうオフターゲット問題という課題が内在する。本研究では、GSPOアルゴリズムの改良を通じてこのオフターゲット問題の抑制を図り、モノリンガルコーパスを用いた、よりロバストかつ高品質な機械翻訳モデルの実現を目指す。 | |
| 課題名 | VLA for Human-Robot Interaction Using Human Action Datasets |
|---|---|
| 氏名(所属) | CAO YONGPENG(東京大学 情報学環・学際情報学府) |
| 利用システム | Miyabi-G |
| This project aims to enable robots to interact intuitively with humans by enhancing VLA models. We will address the critical lack of specialized training data by developing a novel framework that transfers knowledge from human action datasets to the robotic domain. This approach will teach the model to understand dynamic human motion and generate contextually appropriate robot actions for seamless HRI. | |
| 課題名 | 代替推進剤ホールスラスタのプラズマ不安定性の抑制に向けた解析研究 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 松倉 真帆(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G・Miyabi-C・Wisteria/BDEC-01 Odyssey |
| 高い推力密度と比推力を特徴とするホールスラスタは、軌道遷移や姿勢制御を伴う多くのミッションで活用されてきた。キセノンの価格高騰や埋蔵量枯渇、大気利用電気推進機のコンセプト研究の波を受け、水や大気といった軽量推進剤の利用に注目が集まっている。放電室内部で推進剤の電離とイオン加速を同時に実現する構造上、推進剤ごとに最適設計が必要となる。推進剤利用効率の向上と電離の安定維持が課題となる中で、ホールスラスタの高磁場下での異常輸送をいかに抑制できるかが重要となる。本研究では、磁場を横切る方向に電子が輸送される異常輸送の大きな要因と考えられている電子のサクロトロン運動に起因するプラズマ不安定性の時間発展を対象とし、特に軽量推進剤を用いた際の成長フェーズを解析、抑制手法を提案することを目的とする。 | |
| 課題名 | 自己教師あり学習とMHDシミュレーションによる分子雲内の恒星質量の推定 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 平島 敬也(理化学研究所) |
| 利用システム | Miyabi-G・Miyabi-C |
| 本課題は、観測適用を見据え、高解像度3D磁気流体シミュレーションと深層学習を統合し、生まれたばかりの恒星(原始星・前主系列星)の質量を少量のラベルで推定する手法を確立する。Miyabi-cで生成した合成フラクタル画像1,000万枚によるDINOv2の自己教師あり事前学習をMiyabi-g上で実行し、得られた表現を3Dシミュレーションから投影した2Dガスマップに適用、ゼロショットk-NNとfine tuningで性能を評価する。先行実験(100万枚学習)で示した教師あり学習同等以上の性能と主成分分析による意味構造の可視化を起点に、データ・モデル規模に対する収束性、attention mapに基づく合成データ改良、観測ノイズへの頑健性を検証を試みる。最終的に、初期質量関数起源の理解に資する高精度かつ解釈可能な恒星質量推定手法の構築を目指す。 | |
| 課題名 | 神経変性疾患に対する分子結合予測を用いた創薬戦略 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 松田 和己(浜松医科大学 細胞分子解剖学講座) |
| 利用システム | Miyabi-G・Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| 本課題は、アルツハイマー病やパーキンソン病に代表され、認知・運動機能を障害することで知られる神経変性疾患の病態形成に深く関与するα-synuclein多量体と標的分子UBL3の結合構造を、in silico手法により解明し、新たな創薬基盤を確立することを目的である。従来の実験的手法の多くはモノマー構造を対象としてきたが、本課題では患者体内に存在する巨大かつ多様な多量体構造を対象に、AlphaFold3など機械学習による高精度予測と、Cryo-EMデータに対する量子化学計算手法による実データの解析を組み合わせ、網羅的かつ大規模に結合様式を同定する。これによりUBL3の結合ドメインと作用機序を明らかにし、阻害剤やモジュレーター設計に資する。同時にα-synucleinの立体構造予測により神経変性疾患の病態解析に有用な基盤情報を提供する。また、本課題で確立されるパイプラインは神経変性疾患のみならず、様々な創薬における初期段階での低コストかつ効率的なスクリーニング手法を提供するものである。そしてUBL3という未開拓標的を扱う独創的研究であり、神経変性疾患に対する新規創薬戦略に広く貢献する。 | |
| 課題名 | POI グラフ拡張型 RAG による大規模言語モデルの都市知識推論強化 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 徐 小航(東京大学 情報理工学系研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| 本研究課題「POIグラフ拡張型RAGによる大規模言語モデルの都市知識推論強化」は、都市空間データと大規模言語モデル(LLM)の融合を目指すものである。従来のRAG(Retrieval-Augmented Generation)は外部テキストを統合する手法として有効である一方、POI(Point-of-Interest)が持つ空間的近接性や階層的関係、時系列的変動といった構造情報を十分に活用できていなかった。本研究では、POIをグラフ構造として整理し、距離・カテゴリ・利用者行動に基づく関係性を検索・推論過程に組み込むことで、従来困難であった複雑な制約条件下での都市知識推論を可能とする。さらに、検索・推論に用いたグラフ構造を回答に根拠として提示する仕組みを導入し、LLMのブラックボックス性を緩和しつつ透明性を高める。これにより、都市生活者や観光者、自治体に対して高信頼な情報アクセス基盤を提供し、都市情報学・自然言語処理・知識グラフ研究を横断する新たな学術的フロンティアを切り開くことを目指す。 | |
| 課題名 | OpenFOAMを用いた家屋周りの流れ構造の解析と垂直避難リスク評価 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 井野川 七虹(神戸大学 工学研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| 一般的に避難行動には「水平避難」と「垂直避難」が存在するが、屋外への避難が危険な場合は、「垂直避難」が推奨される。しかし、「垂直避難」を実施するためには建物が倒壊・流出しないことが条件となるため、家屋被害を正確に予測することが人的被害を軽減するためには不可欠である。本研究では、OpenFOAMを用い家屋周りの三次元流れ構造を多数の水理条件で解析することで、水理条件と家屋被害の関係から「垂直避難」すべきでない家屋を抽出する。また実事例を対象に三次元の洪水氾濫解析を実施し、家屋被害の説明可能性を検討する。解析には、OpenFOAMのinterFoamソルバーを用い、LESで解析を行い家屋周辺の渦の生成・剥離といった複雑な流体構造を詳細に解析し、流体力を評価する。 | |
| 課題名 | RoleKG: 役割認識型知識グラフ拡張LLMによるパーソナライズ質問応答 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 楊 博銘(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| 本研究では、ユーザプロファイルや対話履歴から構築される動的・個別化知識グラフと指定された役割コンテキストを組み合わせた新しい質問応答枠組みを提案し、パーソナライズ性向上、一貫した役割保持、および説明可能な応答生成を目指します。これにより教育、医療など高信頼性が求められる分野への適用を図ります。 | |
| 課題名 | 細胞基盤モデルの構築のためのメタ条件を活用したアンペア・マルチモーダル学習法の開発 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 岩本 侑一郎(東京大学 先端科学技術研究センター) |
| 利用システム | Miyabi-G |
| 細胞は多様な分子情報や表現型を動的に変化させるため、これらを網羅的に計測し、マルチモーダル解析を行うことが求められる。しかし、同一細胞からのマルチモダリティー計測は現状困難である。そこで本研究では、同一患者や同一時刻といったメタ条件を活用し、ペアデータなしで異なるモダリティーを統合解析するアンペア・マルチモーダル学習法を提案する。 | |
| 課題名 | Unified Speech Representation for Next-Generation Speech AI Models |
|---|---|
| 氏名(所属) | Huang Zhijie(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G・Wisteria/BDEC-01 Aquarius・mdx |
| This project aims to solve the input/output asymmetry in Speech Language Models (SLMs). We propose a novel tokenizer that creates a unified, compact, and disentangled speech representation. It unsupervisedly separates speech into a single stream of content tokens and a global style embedding. This symmetrical approach eliminates complex pipelines, enabling simpler and more powerful speech AI for generation and understanding. | |
| 課題名 | 3次元一般相対論的磁気流体計算で探る中性子星自転周期多様性の起源 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 篠田 兼伍(東京大学 理学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G・Miyabi-C |
| 本研究は中性子星の自転周期、磁場強度、降着率を変えながら中性子星へのフォールバック降着流の3次元一般相対論的磁気流体力学計算を行う。これにより、中性子星が獲得または失う角運動量を定量的に求め、中性子星の自転周期の時間進化の理論モデルを構築する。また、降着率には申請者が独自に導出した超新星爆発の状況から物理的に期待されるフォールバック降着率を採用する。したがって本研究が達成された暁には、超新星爆発機構とパルサー自転周期の多様性を初めて定量的に結びつくと期待される。 | |
| 課題名 | Interpretable Speech Representation Learning for L2 Pronunciation Assessment |
|---|---|
| 氏名(所属) | MCINTOSH, Stephen Eduardo(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G・Wisteria/BDEC-01 Aquarius |
| This project develops interpretable, disentangled speech representations using self-supervised learning to analyze differences between native (L1) and second-language (L2) pronunciation. By decomposing speech into human-understandable components (phonetics, prosody, speaker characteristics), we can provide comprehensive pronunciation feedback that distinguishes genuine errors from acceptable variation, helping L2 speakers improve their communicative effectiveness. | |
| 課題名 | 分子雲コアにおける星形成可能性の予測 -観測・数値シミュレーション融合データを用いた自己教師あり学習 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 野崎 信吾(九州大学 理学府) |
| 利用システム | Miyabi-G |
| 星がいつ・どのように誕生するのかを理解することは、星形成過程の解明にとどまらず、銀河構造の進化や惑星形成の初期条件を知るうえでも重要である。星は重力に支えられた高密度ガス塊(分子雲コア)の収縮によって誕生すると考えられてきたが、近年の観測では重力に支えられていない高密度コアも多数発見されており、それらが将来星形成に至るか否かを判断することは観測データのみからは困難である。本研究では、観測された分子雲コアの将来的な星形成可能性を検証することを目的とする。そのために、Herschel宇宙望遠鏡のアーカイブから得られる数千点の観測データと、申請者がスーパーコンピュータで実施した数万点規模の数値シミュレーションデータを組み合わせ、自己教師あり学習を用いた表現学習を行う。モデルには解像度非依存で特徴抽出が可能なTransformerベースのDinov2を採用し、フラクタル構造やノイズを用いた事前学習の後に観測・シミュレーションデータで追加学習を行う。得られた特徴表現に基づき、①星形成可能性の判定、②将来誕生する星の質量予測を実施する。 | |
| 課題名 | 光学機能材料に向けたDNA修飾ナノ粒子結晶の電磁応答解析 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 池内 泰士(名古屋大学 工学研究科) |
| 利用システム | Miyabi-C |
| 近年、貴金属ナノ構造を利用した表面増強ラマン散乱(SERS)が注目されている。SERSは貴金属ナノ粒子などのプラズモン材料の近接場により、その近傍に位置した分子からの散乱光が大幅に増幅される現象である。DNA修飾ナノ粒子(DNA-NP)結晶は、貴金属ナノ粒子とDNAで構成されることから生体適合性に優れ、構造の設計自由度や再現性が高いことから、生体内に導入可能でかつ安定してSERSを発現する光学プローブとして有望である。しかしながらDNA-AuNP結晶はナノ粒子の配列や大きさが多様で、電磁場応答の理論的記述にはシミュレーションが必要不可欠である。そこで本課題では、MATLABのツールボックスであるMNPBEMを利用した境界要素に基づく電磁場計算により、多種粒子から成るDNA-NP結晶における光電場強度の評価を行う。この手法を用いることで、プラズモンの集団的な共鳴、構造ごとの電磁場分布、光の内部反射の様相などを評価し、複雑かつ多様な光学現象を明らかにする。 | |
| 課題名 | 磁気圏・電離圏観測データに基づく5次元ドリフト運動論的リングカレントモデルを用いたULF波動の励起の研究 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 山本 和弘(名古屋大学 宇宙地球環境研究所) |
| 利用システム | Miyabi-C |
| 本研究では、地球内部磁気圏でみられるリングカレントを形成するような高エネルギーイオン(リングカレントイオン)について、ドリフト運動論的な5次元ブラソフ方程式とマクスウェル方程式を自己無撞着に解く数値シミュレーションを行います。シミュレーションで得られたイオンの時間発展と、イオンとの波動粒子相互作用で励起する超低周波(ULF)波動を調査し、ULF波動の励起メカニズムを明らかにすることを目的とします。磁気圏における単独衛星の観測では、ULF波動の励起状況や荷電粒子の位相空間密度の空間的な広がりを把握することが困難なため、イオンとの相互作用によるULF波動の励起メカニズムを解明する際の障害となっています。そこで、波動や粒子の空間分布を得ることができるグローバルなリングカレントモデルを用いることで、数値シミュレーションの観点からULF波動の励起の理解を深めることを目指します。 | |
| 課題名 | 気候ティッピングリスク評価のための地球システムモデル不確実性定量化 |
|---|---|
| 氏名(所属) | 久保 亘(東京大学 工学系研究科) |
| 利用システム | Miyabi-G・Miyabi-C |
| 気候変動リスク評価を実現するために観測データと融合したリスクの定量化手法の開発が急務である。特に、大西洋子午面循環の弱化やアマゾンの熱帯雨林の大量枯死など地球システムに内在する不可逆な変化である気候ティッピングのリスクを事前に推定することは気候変動対策の数百年スケールでの長期対策を実現する上で非常に重要である。しかし、気候ティッピングは、現代的な観測機器を用いて直接観測されたことのない現象であるので、その予測を行うことは非常に難しい。よって、想定される観測と地球システムモデル(ESM)を用いて気候ティッピングがどれだけ予測可能なのかを検討する必要がある。ESMのパラメータ推定に大きく影響を受ける(Kubo & Sawada,2025) ため、ESMのパラメータのもつ不確実性を観測により評価することが気候変動リスクを定量化する上で重要である。しかし、高次元で長期間の観測データをもとにESMのような大規模なモデルのパラメータを評価し、さらには気候ティッピングという長時間スケールの現象を扱うには非常に大きな計算コストを有する。本研究では、上記の課題を実現する不確実性定量化手法を開発する。 | |